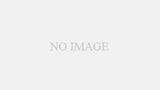(財)石川県産業創出支援機構の「石川発!お店探訪記」金沢・加賀・能登 頑張るお店 では、石川県内の実店舗・ショップを訪問し、取扱商品の特徴・売れ筋、店づくりや店舗展開・経営方針、顧客サービスや今後の課題などを取材して、頑張っているお店の魅力を紹介していきます。
金沢・加賀・能登 頑張るお店 干場金物店(ふくべ鍛冶)
道路拡幅にともなって各個店が新築され、明るい街並みに生まれ変わった能登町宇出津・新町通り商店街。
その中に、漁師が使う万能包丁である「マキリ」をはじめ、鋤(すき)や鍬(くわ)に代表される農作業道具など、鍛冶技術をいかんなく発揮し、顧客のニーズにきめ細かく対応することで、堅実な商いを続けてきている干場金物店(屋号 ふくべ鍛冶)がある。
3代目の主人・干場勝治氏にモノづくりにかける思いを伺った。
●鍛冶の技を代々受け継ぐ
昭和37年、先代の後を継ぐべくこの仕事に就いた勝治氏は、仕入れ販売の仕事の傍ら、高知の土佐刃物、福井の越前刃物、大阪の堺刃物の産地へ修業に出かけ、火づくりの技術や仕上げ技術を研鑽し、自らの技能向上に努めた。
「その当時は、農家に耕運機が普及する前で、刃先が3本に分かれた鋤で田を起こし、鍬で畦ぬりをしていた時代だっただけに、とりわけ春先は農作業に使う道具づくりに大わらわの日々でしたよ。」と若い頃を述懐する。
例えば、鍬一つ例にとっても、使う土地の土質によって刃の形状、柄と刃の角度、柄の長さが異なる。砂地の場合は、鍬を打ち込むというよりも引く感じで使うため、柄と刃の勾配が強い方が良い。粘土質の土地の場合は、深く掘るため勾配が少ない方が良いといった具合だ。
鍛冶仕事からこなす同店は、そうしたニーズにきめ細かく対応できることから、顧客一人ひとりのオーダーメイドに、昔から当たり前のように対応してきている。しかも、宇出津地区は、海にも山にも近いことから、両方の作業で使う道具が求められ、漁師の道具から山仕事の道具までバリエーション豊富な品揃えだ。
かつては、土建業者からの鶴嘴(つるはし)や道具類の注文や修理もかなりあったようだが、建設機械が普及したことから、今はほとんど需要が無くなっているとのこと。 「道具づくりは、すべてお客さんから教えられて、身につけてきたものですよ」と淡々と語る。
●一点一点に全神経・技を傾注
「全ての品物が一点一点手づくりで、全てニーズが異なることから、全てが勉強になり、これでいいということはなく、刃物は切れ味が悪かったらもう次の注文はないわけで、自分が納得できるまで徹底的に研ぐこと、刃付けをしっかりすること、それによって長持ちする商品に仕上げることに専念しています。死ぬまでお客さんの要望との闘いですよ。」と職人魂を垣間見せる。
鍛冶仕事、研ぎ仕上げ、柄付けという三部門の仕事を全て一人でこなし、店頭には使うばかりの状態に仕上がった商品が所狭しと並べられている。鍛冶屋の仕事は、商品を納めたら終わりではなく、研ぎ直し、刃・柄の付け替えなど、アフターフォローが大切で、親子2代・3代の付き合いが多いとのこと。
能登町宇出津地区にも30年ほど前までは3軒の鍛冶屋があったが、時代の変化や後継者問題等で廃業が相次ぎ、残ったのは同店ただ一軒となった。同店も鍛冶屋の仕事だけではとても生き残ることは難しく、仕入れ販売のウエイトを高めることや修理の仕事を確保するなど、さまざまな努力を積み重ねてきて今日がある。
●情報発信が新たな顧客開拓につながる
釣り雑誌や能登町商工会のホームページを通して自店のPRを掲載したのがきっかけとなり、県外からも注文が入るようになってきている。
本来は、漁師が使うための万能包丁であるマキリを、釣り人が使ったり、山へ持っていく、盆栽に使うといったように、使い手が新たな用途を開拓して注文してくるようになっている。さらには、顧客の要望に応えていくうちに、囲炉裏で使う五徳や自在鉤、燭台などといった生活雑貨まで手がけるようになり、顧客の範囲も商品のバリエーションも、一昔前には考えられなかったほど広がり、そうした県外からの注文が全体の1割近くを占めるようになっているという。
地元の農林水産業者の減少や機械化の進展による需要減という逆風下にあって、このことは同店の将来に向けて明るい材料になっている。「今ではお客さんの範囲が広がって、鉄を打って作れる道具であれば、何でも作る便利屋みたいになっていますよ」と顔を綻ばす。
●観光客にも人気のスポットに
県が発行している「ぶらり能登ガイドブック」という観光客向けの情報誌が、能登空港やホテル・旅館などに置いてあり、それを見た若い夫婦連れの観光客がしばしば訪れるという。
特に、週末や連休、夏休み期間になると、そうした観光客が来店し、ご主人が丹誠込めて仕上げた昔からの道具類やナイフ、包丁などを興味深げに眺め、家庭で使う包丁や燭台、囲炉裏セットなどを買い求めていく。
「若い世代の人たちが、こうした伝統的な道具類に関心を持ってくれることは本当に嬉しいことで、私たちも観光客の人が来てくれると話が弾んで楽しいです」と満面の笑みで語ってくれた。
●道具の魅力や、使い方を正しく周知
毎月15日に商店街が実施する「まんなか市」において、商店街散策中に刃物を研ぐ体験をしてもらう即日対応できるサービスを行っているほか、年に数回程度、近所の主婦を集めて、家庭用包丁の研ぎ方教室を開催している。
毎日使う包丁に愛着を持って長く使ってもらうことも、作り手にとっては大切な仕事である。包丁は正しい研ぎ方さえ身につけていれば、かなり長い間切れ味を維持したまま使うことができるだけに、その技術を伝えたいと、店内には包丁研ぎを体験できるコーナーも設けてある。
「長年使って柄が腐って取れてしまった包丁を送ってきて、柄を付け替えて欲しいといった注文が時々ありますが、私ら職人からするとこうして大事に使ってもらえることが何よりも嬉しいですよ」と満足げに語る。
これからの店づくりについて伺うと、「大学を出て地元に戻って就職した息子が、時々経営面のアドバイスをしてくれていますが、将来的には後を継いで頑張ってもらえるように繁盛させていかないと・・・」とご子息に託す思いがひしひしと伝わってきた。
近いうちに自店のホームページを開設し、さらなる新規顧客獲得につなげていきたい意向である。石川県でも職人がほとんどいなくなった伝統の鍛冶技術を是非とも次の世代に伝えていってもらいたいと願わずにはいられない。
■インタビューを終えて・・・
鍛冶職人と聞いて、頑固親父を想像して伺ったが、ソフトな物腰と優しい語り口にまず驚かされた。よくよく伺うと、趣味で詩吟を嗜む粋なご主人であることが分かった。時代に即した商いのやり方を柔軟に模索しながらモノづくりに取り組む姿勢が、生き残りの鍵を握っているのではないだろうか。
火と対峙しながら鉄を鍛える時の妥協を許さない厳しい職人の眼差しが印象に残った。
(平成19年12月取材)
商 号 干場金物店
所在地 鳳珠郡能登町字宇出津新23
創 業 明治41年
電話番号 (0768)62-0785
営業時間 7時30分~19時30分
定休日 不定休